駅商業施設 プロジェクトストーリー
「Komatsu九」
メンバー紹介

後藤 孝
金沢総合事務所 課長代理

久谷 勇樹
まちづくり事業本部 事業開発部 事業開発課 主任
2018年 新卒入社

石内 祐輔
まちづくり事業本部 事業推進部 事業推進課 担当課長
電車を待つ高校生たちの居場所がない
Q.JR小松駅前の再開発。いくつか課題があったそうですね。
 後藤
後藤
一番の課題としては、電車通学している高校生たちが時間待ちをする場所がなかったことです。
駅周辺には5つの高校があるんですが、時間によっては電車が1時間に1本程度なので待ち時間が長い。そうすると必然的に、コンビニでパンなどを買って駅前の広場に座り込んでしまう。ゴミが散乱するし美観も損なわれてしまうという状況が続いていました。
学生だけでなく、駅を利用する地域の方々も同様です。電車待ちの時間に、安心して腰をおろせる場所がないというのは居心地が悪いですからね。
 久谷
久谷
また、JR小松駅周辺にはオフィスや小松大学があるのですが、施設内の食堂が十分に整備されていないことから、昼食需要が満たされていなかったんです。とくに大学内には学食がないので、コンビニに行くかお弁当を持参するしかない。近くに商店街はあるけれど、コロナ禍で閉店するお店も増えていて、それはそれで地域の課題でもありました。
Q.北陸新幹線が開通する駅なのに、なんとか改善したいと。
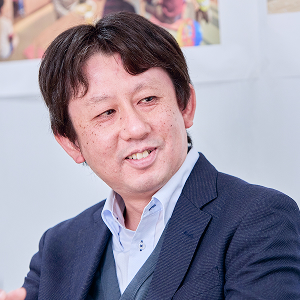 石内
石内
ちょうど新幹線の開通に合わせて、駅全体のリニューアル工事を行っていた時期です。
新幹線のホームや駅舎全体の計画設計はJR東日本建築設計が行っていて、駅前再開発についても目が向けられていた。もともとあったショッピングフロアも古くなっていたので、小松市と共同でリニューアルすることになったのです。
 後藤
後藤
ショッピングフロアのフードエリアを運営していた当社としては、昼食の課題や高校生たちの居場所をどう作ってあげられるか。小松市様とも連携しながら、開発を進めていくことになりました。
とはいえ、駅前の「たまり場」から流れを変えるのは、そんなに簡単ではない。自発的に移動してもらえるだけの魅力がないと難しいだろうなと。
駅構内に自走できるフリースペースをつくろう
Q.どのように企画を進めていったのですか?
 後藤
後藤
高校生たちが集まれる場所となるには、無料のスペースであること。そうでないと駅前広場から移動する価値がないですから。そのうえで、コンビニなどで購入したフードを自由に食べられたり、机があって勉強したり、ゆっくりお喋りできたり。
そういうフリースペースをと考えていたときに、以前からのお知り合いであった社会福祉法人の佛子園さんという会社に声をかけてみたんです。
商業施設「Komatsu九」のコンセプトが「とどまれる場所」となった経緯や、小松駅前が抱えている課題をご説明したところ、すぐに快く引き受けてくださった。駅の改札口正面の75坪、メインの区画で展開していただくことが決まったのです。
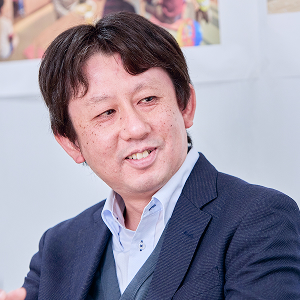 石内
石内
後藤さんが10年以上前に飛び込み営業をかけた法人さんです。フリースペースといっても、店舗のような設えになっていて冷暖房も効いている。フードホールのように食事も提供しますが何も注文しなくていいし、持ち込みもOK。

Q.飲食の収益が見込めないと、運営費はどこから捻出を?
 後藤
後藤
普通ならそこがネックとなって実現不可能になるのですが、今回は違ったのです。
地域の課題がもう一つあって、障がい者雇用の受け皿が少ないことがあった。そこで施設全体の清掃活動を障がい者の方々にお願いできるよう小松市に働きかけまして、その受注元をフリースペースを運営する社会福祉法人(店名:小松KABULET)にしました。
小松KABULET様には、清掃事業の収入が入ると同時に障がい者雇用の補助金が支給されることで、運営費にあてていただける。フリースペースの収益だけではなく、単体で自走してもらえる施設にすることができました。
 久谷
久谷
このアイデアは本当にすごい!後藤さん、よく思いついたなぁと思いました。
 後藤
後藤
いやいや、私のアイディアではなく、佛子園様と小松市様と三者で何度もお打ち合わせして形になっていったものです。駅のコンコース前なので、上手くいかないと大変ですから。最終的には小松KABULET様が承諾してくださってこそ実現したアイデアです。
話を進めるうちに、障がいをお持ちの方には、通勤の利便性がとても大事なことを知りました。たとえば、駅前の道路をひとつ渡るだけでもハードルが上がってしまう。そういう意味でも、駅直結の場所で展開できてよかったです。

「こんな時期に出店?」コロナ禍で奔走したリーシング
Q.フリースペースは早くにまとまったが、他のリーシングで苦労されたとか?
 後藤
後藤
ちょうどリーシング活動を本格化させ始めたのが2021年の1月。コロナの二度目の緊急事態宣言が発動されたタイミングでした。
小松市を代表するエリアとして、できるだけ地元の飲食店さんや食材をとお声がけしても、なかなかいい返事は返ってこなかったです。とにかく電話をかけて、コンセプトを説明させてもらってという日が続きました。
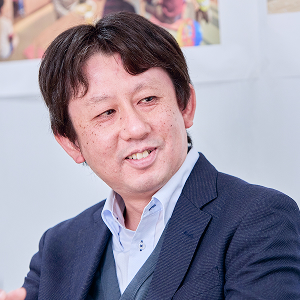 石内
石内
リーシング活動って対面でないと難しいのですが、コロナ禍なので会いに行くことができなかったんですね。私たち本社サイドもオンラインでは連携を取っていましたが、移動は自粛せよという風潮だったので、現地は大変だったと思います。

Q.誰もが足踏みしていた時期ですからね。
 後藤
後藤
先が見えない状況のなか、どの開発案件も費用はできるだけ抑えるようにと言われていました。この案件も「そもそも今やる必要があるのか?」という声もあがっていたようで、そこを本社チームが説き伏せてくださった。
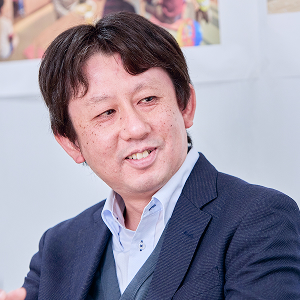 石内
石内
正直いろんな意見がありました。でも結果的には、グループがめざす地域共生企業として、駅前の美観や治安を守っていくべきだろうとなった。
 久谷
久谷
テナント様に対しても、「これから小松駅周辺が変わっていく」という将来構想は、大きな説得材料になりました。すぐ近くでも北陸電力様がビルを建設中で、オフィスやホテル、大学院が入る予定なので人口もかなり増えていく。一緒に小松の街を良くしていきたい、という思いに共感いただけたのだと思います。
Q.内装工事でハプニングもあったとか?
 後藤
後藤
はい(笑)、フリースペースの工事が進んだ段階で、内装デザインを大きく変えたいと。
聞いてみると、コロナ禍で駅前商店街の50店舗ほどが閉店になり、高齢者の方たちの行きつけの場所がなくなってしまった。「そんな方々が集まれる場所にもしてあげたい」と聞いて、それならと大急ぎで計画変更したんです。
最初はおしゃれなカフェ風だったのですが、ガラッと変わりました。閉店されたお店から照明や絵画をもらってきたり、古すぎて再利用できない家具は似せて作ったものもあります。駅舎の工事中で搬入も分刻みというなか施工会社さんには大変なご苦労をかけたのですが、地元の方たちが落ち着ける場所にもできました。
 久谷
久谷
「カブーレ」というネーミングは「ごちゃまぜ」という意味らしくて、学生も高齢者も障がい者もみんなごちゃまぜで、気持ちのいい空間をつくりたいというコンセプトなのだそうです。
みんなを受け入れてくれる雰囲気があって、さらに無料だからいろいろな人たちが自由に集まりやすいのでしょうね。
JR小松駅からはじまる街づくり
Q.実際にリニューアルされて、高校生たちの様子は?
 後藤
後藤
それがね、駅前広場が見違えるほどきれいになったんです!もう座り込む学生もいません。
しかも、フリースペースでは勉強している学生さんをよく見かけるようになりました。コンセントやWiFiも整っているので。食べたお菓子の袋も、ちゃんとゴミ箱に捨ててくれています。
 久谷
久谷
小松市様や佛子園様と共にGOODデザイン賞をいただいたんです。交流スペースで地域のコミュニティ形成に貢献したということで受賞しました。

Q.まさに「Make PLACE(コミュニティ形成を支える仕掛け)」ですね?
 後藤
後藤
今では様々なイベントも催されていて、課題を持ちよっては形にしながら解決策が見つかっている様子です。デベロッパーが押し付けるのではなく、自然につながりができていく場をいかに作るかが「Make PLACE」なんだなと。実際にKomatsu九が開業してから、関係人口が急激に増えてきているともきいています。
 久谷
久谷
今は次のステップに進んでいて、小松の街づくりにまで広がってきている。
 後藤
後藤
ここが想像以上に盛り上がったので、小松市からも「Komatsu九を人・物の交流拠点として、賑わっていない地域にもにじみ出していきたい」と。今いちばんの課題はシャッター商店街化しているエリアで、商店街や小松市のご担当者と相談しながら動き出しています。
小松市は昔から繊維が盛んだったり、小松製作所などメーカーが育ってきた街でもあるので、小松市長はここを拠点にものづくりの街として盛り上げていくという政策を打ち出しています。


Q.「JR小松駅からはじまる街づくり」ですね。
 後藤
後藤
当初は、Komatsu九が完成したらプロジェクトは完了すると思っていたのですが、うれしい誤算です。
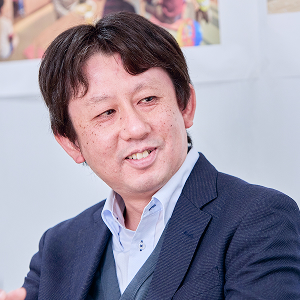 石内
石内
コミュニティ形成に取り組む「Make PLACE」、コンセプトである「駅からはじまる街づくり」。今回はそのどちらにも通じる成功事例だと思っています。沿線各地には同様な課題をかかえる地域も多くありますから、これから若い人たちの柔軟な発想と行動力がますます大切になってくると思います。
プロジェクトを振り返って
思うこと

予算が限られていたので、とにかく工夫の連続でしたが、それも逆にいい経験になりました。
たとえば、膨大な予算がついている新幹線側駅舎の外壁と同じものは使えないけれど、できるだけ近い質感を出すためにはどんな素材や塗料があるか?いろいろな建材を探して、結果的にはいいものができあがりました。
他のメンバーと距離は離れていましたが、本社と金沢拠点の垣根は全くなかったです。コミュニケーションもうまく取れていたので意思決定もスムーズに進められたと思います。

今日久しぶりに小松に来て、小松KABULETさんの「いいごちゃまぜ感」を肌で感じました。
そんな風景を見ていると、デベロッパーとして収益物件をつくることは大事なんですが、それだけではない部分にも目をむけることで「Make PLACE」により近づいていけるように思いました。
※ 所属部署は、インタビュー当時の部署を掲載しております。

